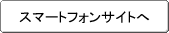消化器の薬

食欲不振、嘔吐、便秘、下痢などの症状をひきおこす消化器(胃や腸)の病気は、
イヌには日常的にみられるものです。とくに多い病気に次のようなものがあります。
★胃炎・胃潰瘍
腐敗した食べものや異物、有害な化学物質などを食べると胃の粘膜が
そこなわれ、急性あるいは慢性の炎症がおこります。これが胃炎で、
症状が進むと胃の粘膜に傷ができて胃潰瘍となります。
細菌やウイルスの感染、あるいはイヌでも精神的なストレスが原因で、
胃炎や胃潰瘍になることがあります。
★小腸炎
これも腐敗した食べものなどが原因で小腸の粘膜に炎症ができる病気です。
症状としては下痢がもっとも多く見られます。
ウイルスや細菌、寄生虫の感染が原因のこともあり、まれに食餌性アレルギー
(食品中にふくまれる特定の物質に対するアレルギー反応)による小腸炎もおこ
ります。
小腸炎はしばしば胃炎を併発し、胃腸炎となります。
パルボウイルスの感染による胃腸炎では、急速に悪化して死亡することが
あります。
★大腸炎
大腸の粘膜は水分や電解質を吸収するところです。
この粘膜が炎症をおこして大腸炎になると、下痢を起こします。
大腸炎では粘液がまじり、腸壁に潰瘍ができると血液も混ざります。
胃炎や胃潰瘍の治療薬としては、胃酸の分泌をおさえる胃酸分泌抑制薬や、
胃酸の酸性度を弱めたり酸を中和したりする制酸薬が使われます。
また、小腸炎や大腸炎では、おもな症状である下痢を止める止瀉薬がよく
用いられます。
●胃酸分泌抑制薬/制酸薬
→胃酸の分泌をおさえる
→胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍の治療によく使われる薬です。
胃酸分泌抑制薬は胃酸の分泌をおさえ、制酸薬は胃酸の酸性度を弱めたり
中和するはたらきがあります。
これらの薬は、作用のしかたによって大きく3つの種類に分けられます。
▲H2ブロッカー
胃壁にある胃酸を分泌する細胞では、化学物質のヒスタミンが細胞膜
にある“鍵穴(H2受容体)”を刺激して、酸の分泌をうながします。
この鍵穴に先回りして結合し、ヒスタミンの作用をさまたげて酸の分泌
をとめるのが、H2ブロッカーとよばれる種類の薬です。
これにはシメチジン、ファモチジン、ラニチジンなどがあります。
消化器の潰瘍の治療によく使われます。
▲プロトンポンプ阻害薬
これは、胃壁の細胞中にある水素イオンを輸送するポンプの機能を
おさえることによって、胃酸の酸性度を低下させる薬です。
オメブラゾール、ランソプラゾールなどがあります。
作用はH2ブロッカーにくらべてさらに強力で、H2ブロッカーでは
治療効果があらわれない潰瘍に用いられます。
▲制酸薬
アルカリ性の化学物質は胃酸を直接、中和するはたらきがあるので、
胃炎や胃潰瘍の治療に使われます。
酸による炎症や潰瘍への影響をやわらげることができます。
炭酸水素ナトリウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウムなど
があります。
▲止瀉薬
→腸炎の下痢を止める
→小腸炎や大腸炎などでおこる下痢を止めるために使います。
これには、麻薬のモルヒネの止瀉作用をまねした薬や、腸の粘膜を
保護して止瀉作用を発揮する薬などいくつかの種類があり、症状に
よって使い分けられます。
▲モルヒネ様物質
モルヒネのもつ止瀉作用に似たはたらきをもつ麻薬効果のない薬として、
ロペラミドがあります。
腸の粘膜には、水分や電解質、栄養分を吸収する細胞と、水分や粘液を
分泌する細胞があり、その吸収と分泌のバランスがとれているときに、
腸は正常な機能をはたすことができます。
麻薬のモルヒネは、腸の水分の分泌をおさえて吸収を高める作用と腸の
運動をおさえる作用をあわせもち、下痢をおさえる効果を発揮します。
しかし、麻薬を治療薬として使うには限度があるため、モルヒネをまねた
物質、つまりモルヒネ様物質としてロペラミドがつくられました。
これは腸の分泌と運動をおさえて食べものが腸内にとどまる作用を
発揮します。
▲収れん薬
腸の粘膜の表面に膜をつくって粘膜を刺激から保護し、
さらに止瀉作用を発揮します。
これには次硝酸ビスマス、タンニン酸アルブミンなどがあります。
おもに腸炎の治療に使われます。
▲吸着薬
腸管内の有害な毒素や細菌、ガスなどを吸着し、下痢を防ぎ、
炎症や潰瘍の治癒をはやめます。
薬用炭、天然ケイ酸アルミニウムなどが薬として使われます。
▲生薬
生薬(植物などに自然にふくまれている薬効成分)のオウレン、
オウバクの一成分であるベルベリンは、腸管の吸収・分泌に作用して
下痢を止める効果を発揮します。
また、腸内の有害な細菌に対する殺菌作用ももち、腸内での腐敗や
発酵をおさえます。イヌの下痢によく使われる薬です。
●運動機能調節薬
→胃や腸の運動を活発にする
→胃や腸の運動を改善し、炎症や潰瘍、下痢などの症状をやわらげます。
脳や神経系に直接作用して胃や腸の運動を活発にするものと、
これらの作用と同時に消化液の分泌を調節し粘膜を保護する作用をもつもの
があります。
▲抗ドーパミン薬
消化機能の中枢は脳幹にあります。
スルピリドやメトクロプラミド、ドンペリドンなどは、この脳幹や、
胃や十二指腸の神経にはたらいて、胃や腸の運動を活発にします
(胃の運動をおさえる生理活性物質であるドーパミンのはたらきを
おさえることで、この効果を発揮します)。
これによって悪心や食欲不振も改善されます。
嘔吐をおさえる制吐薬のはたらきもあります。
▲鎮痙薬
腸の運動は、交感神経と副交感神経という2つの神経に支配されています。
交感神経は腸の運動を逆に活発にします。
このうち副交感神経での情報の伝達は、アセチルコリンという物質によって
おこなわれます。ブチルスコポラミンやプロパンテリンなどの薬は、このア
セチルコリンの作用を止めて副交感神経の興奮をしずめ、腸の運動をゆるや
かにします。
鎮痙薬は胃液の分泌をおさえるはたらきもあり、胃炎をおこりにくくします。
▲健胃薬
漢方薬の成分であるゲンチアナ、センブリ、オウバク、ケイヒなどは、
消化液の分泌をうなします。
また胃や腸の運動を活発にする作用も発揮します。
●抗生物質/合成抗菌薬
→胃や腸の病原細胞を殺す
→消化器の病気はしばしば細菌の感染によっておこります。
この細菌を殺すために抗生物質や合成抗菌薬のサルファ剤が使われます。
抗生物質ではペニシリン製剤がもっとも多く用いられます。
これにはアンピシリンやアモキシシリンなどがあります。
サルファ剤ではスルファモノメトキシン、さらにカナマイシン、
フラジオマイシンなども使われます。
●制吐薬
→嘔吐や吐き気をおさえる
→胃炎や胃潰瘍では嘔吐や吐き気がおこります。
嘔吐を支配する中枢は脳の延髄にあり、これを嘔吐中枢といいます。
メトクロプラミドやクロルプロマジン系の精神安定薬は、この嘔吐中枢に
はたらいて嘔吐や吐き気を止める効果を発揮します。
●生菌剤(整腸剤)
→腸内細菌をおぎなう
→動物の腸内にはたくさんの種類の有用な細菌(乳酸菌、ビフィズス菌など)が
すみついています。
動物の種類や、個体によっても菌の種類が微妙に違います。
これを腸内細菌叢といいます。
これらの腸内細菌は宿主である動物と共生(助け合う)関係にあります。
イヌの大腸にも、大腸の内容物1グラムあたり100億個もの細菌が
生きています。
消化管の腸内細菌叢のバランスがくずれ、下痢がおこると考えられます。
そこで、不足した腸内細菌を外からおぎなってやることで、下痢の症状が
やわらげられる場合があります。
このような生きた細菌をふくむ薬を生菌剤といいます。
最近では、イヌの腸内細菌叢にあわせてつくられた生菌剤も出ています。
生菌剤は副作用もなく、きわめて安全な薬といえます。
●補液剤
→水分と電解質をおぎなう
→下痢がつづくと、体内から水分と電解質(とくに炭酸水素ナトリウム)が
急速に失われていきます。
とくに嘔吐と下痢がいっしょにおこると深刻で、命にかかわることもあります。
このような場合、静脈注射(点滴)や皮下注射によって水分と電解質を補給して
やります。これが補液剤です。
口から飲ませる補液剤もあります(これはスポーツドリンクで代用できます)。
●下剤
→腸からの排便をうながす
→消化器のはたらきが悪くなったり他の臓器の病気が原因で、
便秘になることがあります。
便秘は、便が腸内に長くとどまり腸管に水分が吸収されてかたくなるために
おこります。
このような場合、酸化マグネシウムや硫酸マグネシウムなどを投与すると、
それらは腸管から吸収されずにその中にとどまりますが、浸透圧によって
腸内に水が集まって、便をやわらかくし、排便をうながします。
このような便秘薬を浸透圧性下剤といいます。
また、カルメロースナトリウムを投与すると、腸管内で水を吸収して膨張し
大腸を刺激してやはり排便をうながします。
これを膨張性下剤といいます。
ヒマシ油、フェノバリン、センノシドなどは、腸を化学的に刺激して排便を
うながします。
☆使用の時の注意
細菌などの感染によっておこる消化器の病気を治療するために
抗生物質を長い間使いつづけると、有用な腸内細菌叢のバランスがくずれ、
かえって下痢の症状の慢性化しかねません。
そこで抗生物質は注意して使うべきです。
消化器の機能は非常に複雑にできており、とくに慢性的な消化器病の場合、
原因を特定できないこともよくあります。
ふだんからイヌの食欲や便の状態、嘔吐の有無など、消化器にかかわる
症状をきめこまかく観察し、異常があれば早目に獣医師の診断をあおぐ
ことが大切です。