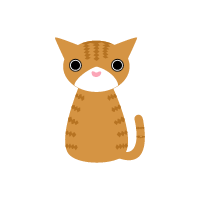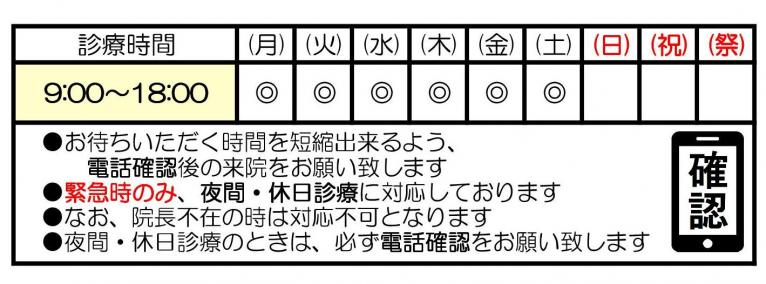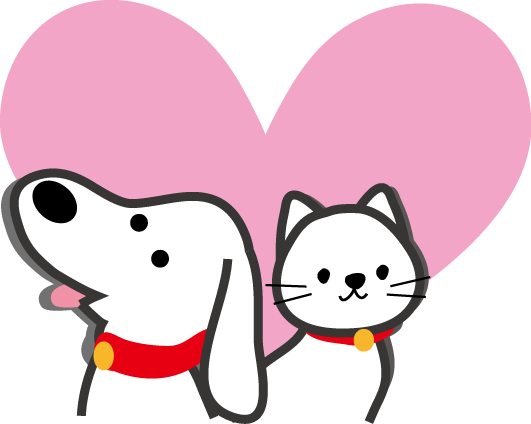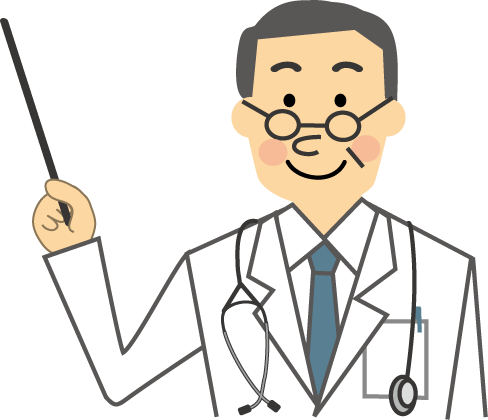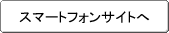栄養性の病気
・肥満
→ネコの肥満は万病の原因
→最近肥満のネコが増えている原因のひとつは、ネコの食生活が向上し、必要以上に栄養価の高い
食べ物を与えられていることでしょう。また都市部で屋内だけで生活しているネコが増えている
ことも、肥満増加の理由と考えられます。彼らはせまい屋内に閉じこめられて運動不足だからです。
ネコは運動能力の非常に高い動物ですが、活動的とはいえず、1日の大半を眠ったりじっとうずく
まるなどしてすごします。こうした性向をもつネコに高カロリーで嗜好性の高い食事ばかり与えて
いては、肥満になるのも当然です。
たしかに治療の必要があるほど病的に肥満したネコはそれほど多くはありません。
しかし肥満気味のネコは非常に多いようです。肥満を病気と考えない人もいますが、少なくとも病気
の予備軍です。ネコが健康に生きるには、肥満はさけるべきです。
こうした傾向を反映して、今では体重を落とすためのネコ用ダイエット食も出まわっています。
あまりにも多様な食べ物が出まわっているため、ネコの食事に頭を悩ませる飼い主も少なくないよう
です。
・黄色脂肪症(イエローファット)
→腹部に硬いしこりができる
→栄養がかたよっていると発症する病気です。ネコの腹部や胸部、腹腔内などにたまった皮下脂肪が
酸化して変性し、炎症をおこします。脂肪は本来きれいな白色ですが、この病気になると黄色く変
色して見えることから「黄色脂肪症(イエローファット)」と呼ばれます。汎脂肪織炎ともいいます。
最近では、栄養のかたよりから生じるこうした病気はあまりみられなくなっています。
これは、多くの飼い主がネコの栄養にも気を配るようになり、また動物用の食品をつくっている企業
も栄養のバランスを考慮するようになって、ネコの食生活が改善されたためと考えられます。
・ビタミンB欠乏症
→魚好きのネコは要注意
→ネコの栄養性の病気の中でも、ビタミンB1の欠乏症はとりわけおこりやすい深刻な病気です。
というのも、ネコはイヌや人間にくらべてもともと大量のB1を必要としているからです。
とくに魚を主体とした食生活を続けているネコは、ビタミンB1が不足しがちです。
この病気は、症状が重くなると立ち上がることができなくなるなどの神経症状が出ます。
そこで飼い主は、ネコの食生活に注意し、この病気を予防する必要があります。ネコはビタミンB1
欠乏症以外にも、ビタミンB2やB6の欠乏症を発症することがあります。
これらの病気の発症はB1欠乏症にくらべるとまれですが、症状は似ており、はっきり区別することは
困難です。
・ビタミンA欠乏症
→偏食ぎみのネコに多い
→ネコの体は、人間やイヌなど他の動物と異なる特徴をいくつかもっています。
そのひとつは、体内でビタミンAをつくることができないというものです。
そこでネコは、体が必要とするビタミンAのすべてを食べ物から摂取しなければなりません。
そのため、偏食ぎみのネコはこの病気にかかる可能性がとくに高くなります。
・ビタミンA過剰症
→骨が変形してもとにもどらない
→この病気は日本では欧米ほどひんぱんにはみられません。
というのも、日本と欧米のネコでは、人間と同様、食生活も違っているためと考えられます。
ネコの食事にキャットフードを利用しないとき、日本ではネコに肉よりも魚や魚の缶詰を与えることが
多いようです。これに対して欧米では一般に、鶏肉や牛肉、それにそれらの内臓、とくにレバーなどを
食べさせる傾向があります。レバーにはビタミンAが豊富にふくまれており、少量ならむしろ体に有益
です。しかしひんぱんに食べると、ビタミンA過剰性をおこす原因になります。
・上皮小体の異常
→骨が変形してもとにもどらない
→この病気は日本では欧米ほどひんぱんにはみられません。
というのも、日本と欧米のネコでは、人間と同様、食生活も違っているためと考えられます。
ネコの食事にキャットフードを利用しないとき、日本ではネコに肉よりも魚や魚の缶詰を与えることが
多いようです。これに対して欧米では一般に、鶏肉や牛肉、それにそれらの内臓、とくにレバーなどを
食べさせる傾向があります。レバーにはビタミンAが豊富にふくまれており、少量ならむしろ体に有益です。しかしひんぱんに食べると、ビタミンA過剰性をおこす原因になります。
・クル病
→骨の成長が止まる
→クル病は食べ物の中のカルシウムが不足するため、骨が成長をさまたげられて変形する病気です。
魚を与えるときに、大きな骨ばかりでなく小骨まできれいにとり除くなどの気づかいが、かえって
こうした病気につながります。この病気はネコではまれで、カルシウム不足が長く続くともむしろ
上皮小体機能亢進症というより重い骨の病気になります。。