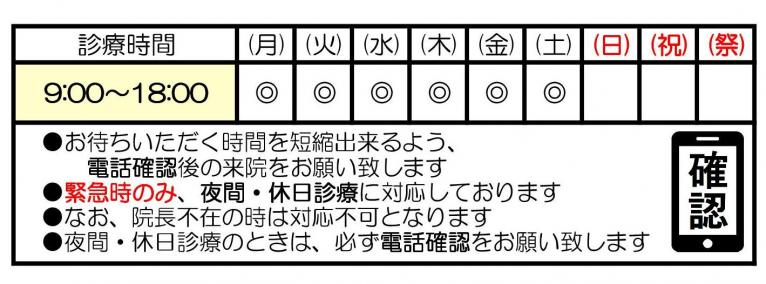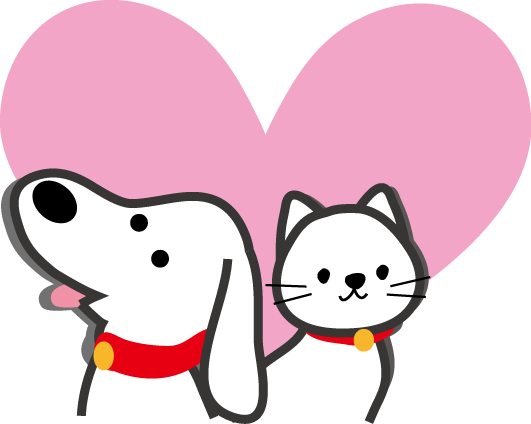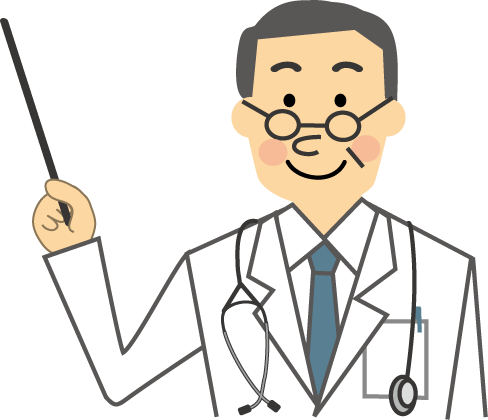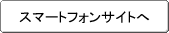内分泌性皮膚炎
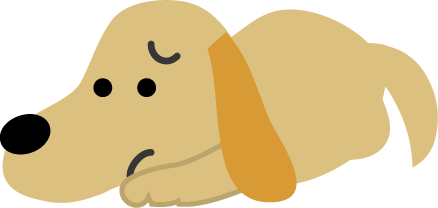
内分泌系の疾患(副腎皮質機能亢進症や甲状腺機能低下症など)は生体の代謝に
変化を与えるが、皮膚や被毛に対してもタンパク合成や細胞分裂の抑制をおこす。
被毛は発育とはえかわりの周期をくりかえしているが、内分泌系の疾患にかかると
この周期が正常に保てなくなり、角化異常などが進行して脱毛をはじめとした皮膚
病変を生じる。
【原因】
分泌量の過不足により皮膚炎をおこすホルモンには、副腎皮質ホルモン
(分泌過剰)、甲状腺ホルモン(分泌過剰と減少)、成長ホルモン(分
泌減少)などがあげられる。
【特徴】
内分泌性皮膚炎は4~5歳齢以上の犬に発症が多い。
初期症状としては脱毛、色素沈着などがみられるが、痒みの認められることは
ほとんどない。
【症状】
副腎皮質機能亢進症では皮膚の菲薄化(皮膚の表皮、真皮部分が病的に薄くな
ること)、色素沈着、脱毛がみられ、甲状腺機能亢進症では脱毛、皮膚の肥厚
の形成、性ホルモンの分泌過剰(セルトリ細胞腫、精巣腫瘍のひとつなど)で
は脱毛、色素沈着、脂漏性の皮膚炎がみられる。
また、甲状腺機能低下症では黒色表皮肥厚症や脱毛がみられ、性ホルモンの分
泌減少でも脱毛がみられる。
特定の部位に脱毛が限局することがあるが、その発症部位から原因となってい
るホルモンとその異常を推測できることもある。
たとえば副腎皮質ホルモンの分泌亢進や成長ホルモンの分泌低下では体幹が広
範にわたって脱毛するが、頭部や四肢の被毛は脱毛しにくい。
性ホルモンの分泌異常では、しばしば生殖器や肛門周辺に脱毛が集中する。
さらに甲状腺機能低下症(分泌減少)に伴う脱毛は左右対称性の場合が多く、
被毛は容易に抜け落ちる。
また副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)でも体幹の左右対称性脱毛が
みられる。
このように脱毛の状態を正確に把握することはその原因を明らかにするため
に重要である。